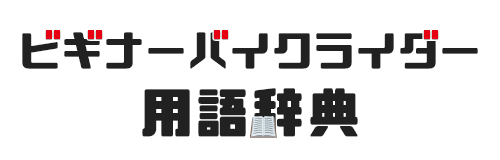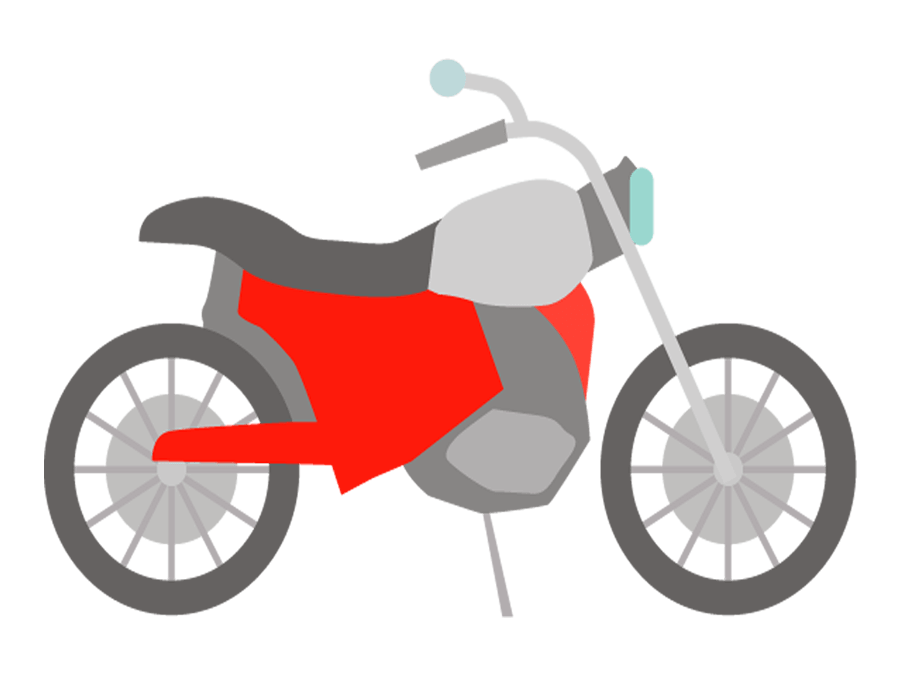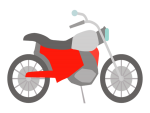二輪車通行禁止が定められている区間
ツーリングをしている時、「二輪車通行禁止区間」に遭遇したことがあるライダーも少なくないでしょう。
この区間はその名の通り、二輪車、つまりバイクが走行できない区間のことです。
二輪車通行禁止区間のせいで、当初予定していたツーリングのルート変更を余儀なくされたという経験もあるかもしれません。
そのような場合、「四輪車である自動車は走行できるのに、どうしてバイクだけ走行できないの?」と疑問に思った人もおられるでしょう。
二輪車通行禁止区間は全国いろいろな場所にあり、なかにはツーリングに向いている道路や観光地に向かう道路なども含まれています。
バイクでの旅を計画する際には、ルート上に二輪車通行禁止区間が無いかを事前にチェックしておくことは大切です。
標識から通行できないバイクの種類がわかる
二輪車通行禁止区間は、標識で通行できるバイクの種類がわかります。
二輪車通行禁止の標識はバイクに乗った人のシルエットに赤い斜め線が入っているデザインですが、シルエットや注記によって通行できないバイクの種類がわかります。
ベーシックなデザインの二輪車通行禁止区間の標識が設置されている道路では、基本的に全ての種類のバイク、および原動機付自転車が通行できません。
バイクに乗った人のシルエットが二人乗りデザインの標識の場合、大型バイク、および二人乗りでのバイクの通行が禁止されています。
さらに二輪車通行禁止の標識に付いている注記からも、通行できないバイクの種類がわかります。
「原付」という注記のある標識の場合、二輪車通行禁止区間は原動機付自転車(原付)の通行ができません。
例えば首都高速道路などがそうで、この標識のある道路では「原付一種」での走行はできませんが「原付二種」なら走行ができます。
「小二輪」という注記が付いている場合、その道路では原付二種も走行できません。
原付を所有している人は自分のバイクが「一種」なのか「二種」なのか、そして「原付」と「小二輪」の注記の違いをきちんと把握しておくようにしましょう。
どんな基準で設置されるのか
二輪車通行禁止区間は、道路幅が狭い場所や二輪車の通行が危険だと判断される場所に設置されます。
代表的な場所に、アンダーパスと呼ばれる道路の下にある道路や、オーバーパスと呼ばれる陸橋などがあります。
こうした道路の多くは「原付」の通行が禁止されていますが、中には全てのバイクが通行できない道路もあります。
また、山岳部の観光地なども二輪車通行禁止区間のところが多くあります。
山岳部の道路は安全面から通行が禁止されているため、時間帯や季節によって通行禁止になるタイミングが変わる道路もあります。
観光地にもこうした道路は多いので、ツーリングを計画する時には事前に確認するようにしましょう。